 |
|
NAF偲偼丂
偛偁偄偝偮丂
妶摦曬崘丂
曐岇嬫徯夘丂
偛婑晬丒偍栤崌偣 僊儍儔儕乕丂 僩僺僢僋僗丂 娭楢彂愋丂 儕儞僋 |
 亂No.48丂2019擭9寧亃 乽愜乆偺偙偲偽乿偵乗亀僸僩丄將偵夛偆亁乮島択幮慖彂儊僠僄乯弌斉婰擮夛乗
擔杮傾僀傾僀丒僼傽儞僪戙昞 9寧13擔偵奐偐傟偨島択幮杮幮26奒夛媍応偱偺亀僸僩丄將偵夛偆亁弌斉婰擮夛偺曬崘偲杮彂偵偮偄偰丄庒姳偺嶨姶傪丅  崱夞丄摿偵傂偲尵傪偍婅偄偟偨偺偼丄埲壓偺曽乆偱偟偨丅 島択幮偐傜 椦曈岝宑偝傫乮島択幮妛弍僋儕僄僀僩戙昞庢掲栶乯 儕儕乕偺庡帯堛偐傜 嵅乆栘怢梇偝傫乮搶嫗戝妛柤梍嫵庼乯崅楊幰偙偦將傗擫側偳偺僷乕僩僫乕摦暔偑昁梫偱偁傞偲丄椡偵側傞尵梩傪捀偒傑偟偨丅 嵟弶偺杮偐傜偺桭恖偲偟偰 彫峀巕偝傫乮塱榓彜帠姅幃夛幮戙昞庢掲栶幮挿乯1997擭偺弌斉婰擮夛埲棃丄搰偺摨憢惗偺拠娫偲偟偰巟墖偟偰偔偩偝偭偰偄傞偺偱偡偑丄乽摨憢惗傪戝愗偵偟側偝偄乿偲鎩尵丅偡傒傑偣傫丅朰傟偰偄偨傫偱偡丅 嵟嬤嶌亀俋偮偺怷偲僔僼傽僇偨偪丂儅僟僈僗僇儖偺僒儖偵夛偄偵偄偔亁乮暉壒娰彂揦乯偺夋壠偲偟偰 媏扟帊巕偝傫偵偼杮偺尨夋傪帩偭偰偒偰偄偨偩偒丄尒偨恖傒傫側姶摦偟偰偄傑偟偨丅傑偨丄暉壒娰偐傜偼崱夞偺奊杮偺扴摉幰杒怷偝傫偵戙傢傝丄愇揷塰屷偝傫乮乽偨偔偝傫偺傆偟偓乿曇廤挿乯偑弌惾偟偰偔偩偝偄傑偟偨丅  亂偍巇帠徯夘亃 傾僀傾僀丒僼傽儞僪偺巟墖幰偵偼丄帺慜偱偺巇帠偑傾僀傾僀丒僼傽儞僪偺妶摦偲儕儞僋偟偰偄傞曽傕偁傝丄偦偺曽乆偺巇帠傪徯夘偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅 斕攧偟偰偄傞僐乕僸乕偺愢柧 戝怷攷偝傫乮僐乕僸乕僲乕僩揦庡乯僐乕僸乕姰攧両 儅僟僈僗僇儖椃峴偺愢柧 怺愳屨師榊偝傫乮摴慶恄乯梊栺偟傑偟偨両擖嬥傕両 朮巕偺惢嶌庴偮偗 徖怟尗帯偝傫乮僓丒儅僢僪僴僢僞乕揦庡乯嵟嬤嶌亀僯僙僐偺12僇寧亁乮LUPICIA乯傪傂偭偝偘偰偺搊応丅慜亀梼偺墹崙亁曇廤挿偱丄崱偼僯僙僐偺朮巕壆偝傫丅梊栺傕庢傟偨傛偆偱偡丅 僌儖僥儞僼儕乕偲恡憻堏怉懱尡偐傜 弜壨偐偍傝偝傫乮Orenge spoon戙昞乯丅斵彈偼2012擭偺儅僟僈僗僇儖尰抧帇嶡偵嶲壛偟偨暯徏傒偳傝偝傫偺挿彈偱丄愮梩導偱妶桇偟偰偄傞搰偺恊懓乮柮偺巕偱柮懛偰偭偦傫丄戝柮偲傕乯偱偡丅戝暔偵側傞丄偙偺恖丅 亂傂偲尵偺帪娫亃 奀忋帺塹戉巌椷挿姱偐傜 曐堜怣帯偝傫乮儅僟僈僗僇儖攈尛楙廗娡戉巌椷姱乯丂2001擭傾儞僞僫僫儕償偱偺楙廗娡戉娊寎夛偱弌夛偭偨壓娭惣崅偺摨憢惗偲偄偆墢偩偗偱丄傾僀傾僀丒僼傽儞僪偵巟墖傪懕偗偰偔傟偨曽偱丄摉擔偺暤埻婥偼偄偐偵傕奀孯巌椷姱偱偟偨丅崱夞偺杮偵偮偄偰偺夁暘側朖傔尵梩偵丄偮偄乽壓娭幰偼榖偑戝偒偄乿偲巹偼尵偭偰偟傑偭偨丅偩偭偰丄乽僲乕儀儖徿傕偺乿偲偐尵偆傫偩傕偺丅 惣崅摨憢惗偐傜 媑愳弴堦偝傫乮姅幃夛幮僕儍僷儞僐儞僺儏乕僞乕僒乕價僗戙昞庢掲栶夛挿乯丂傕偭偲傕怴偟偄桭恖偱丄偙偺9寧1擔偺戝嶃島墘偱抦傝崌偭偨偽偐傝丅斵偑婲嬈偟偨婇嬈梡僐儞僺儏乕僞乕僒乕價僗偺夛幮偼愮戙揷嬫偵杮幮傪傕偪丄戝嶃帠嬈強傕偁傝傑偡丅 朳憤帺慠攷暔娰偐傜 嫶杮朙偝傫丅斵偙偦偼巹偺恖惗偱僯儂儞僓儖挷嵏偺弶傔偵弌尰偟偰丄埲棃40婔惎憵丄庒姳偺徚懅傪抦偭偰偄傞偩偗偱夛偭偨偙偲偑側偐偭偨丅偩偐傜丄乽偦偺摉帪偐傜巘彔偼乿偲偄偆榖傪幷偭偰丄乽崱傑偱偳偆偟偰偄偨傫偩両丠乿偲暦偄偨偺偩偭偨丅幚偵夰偐偟偄嵞夛偩偭偨丅 亀梼偺墹崙亁偐傜 栧慜婱桾偝傫乮曇廤挿乯偲垻晹梇夘偝傫乮僼僅僩僌儔僼傽乕乯尵傢偢偲偟傟偨慡擔嬻婡撪帍偺曇廤挿偲乽僄乕僗僇儊儔儅儞乿偑嬱偗偮偗偰偔傟偨丅僼僅僩僌儔僼傽乕偼乽棃寧傕偁傝傑偡乿偲丄崲擄傪嬌傔傞揤慠婰擮暔庢嵽偼乽偦傕偦傕偁側偨偺敪埬乿偱偁傞偲丄榁嬰偵曏傪懪偮偺偩偭偨丅 搰懽嶰偺摦暔妛偵偮偄偰 墦摗廏婭偝傫乮搶嫗戝妛憤崌尋媶攷暔娰嫵庼乯偙傟偼丄摿偵嫵庼偵埶棅偟偨傕偺偱丄偐偮偰斵偼亀恊巜偼側偤懢偄偺偐亁乮拞岞怴彂乯傪乽晄媭乿偲傑偱帩偪偁偘偰偔傟偨偺偩偑丄偙偺偲偙傠乽儅僢僪僒僀僄儞僥傿僗僩乿婥枴偱偼側偄偐丄偲偄偆偛斸敾偱傕偁傟偽丄偲偍婅偄偟偨丅乽儅僢僪乿偼乽MADA乿偵捠偠傞丅偦傫側傕偺偱偁傞丄偲妎屽偟偰偄偨偑丄堄奜偵傕乽怣擮偺恖乿偲昡偟偰偄偨偩偒乽柺敀偄丄戞擇丄戞嶰偺將偑棃傞乿偲梊尵傑偱偟偰偄偨偩偄偨丅偝偰丄偳偆側傞偐丠 傾僀傾僀丒僼傽儞僪偐傜 儔乕儔嶗偝傫偼丄搰嶌帉丒彲巌棿嶌嬋偺壧傪挘傝偺偁傞惡偱擬彞偟偰偔偩偝偭偨丅怱偑恔偊傞巚偄偩偭偨丅擇斣傕徯夘偟偰偍偒傑偡丅 亙僔儏僶儕僄巀壧偺僥乕儅亜 堦斣 峴偔庤傪偝偊偓傞棐傕塉傕丂偙偊偰椃偡傞丂傢傟傜偺柌偼 偡傋偰偺柦丄偲傕偵懅偯偒丂偡傋偰偺柦丄傗偡傜偐側怷 偼傞偐側摴傪丄偼傞偐側柌傪丂扵偟媮傔偰丄崱擔傕椃備偔丅 扵偟媮傔偰丄崱擔偧椃棫偮丅 擇斣 墛偵姫偐傟傞丂柦傛怷傛丂柍媷偺帪偺丂曮傕偺偨偪 婏愓偺惎偵丄偐偑傗偔怷傪丂庣傝偮偯偗傞丄枹棃偺傂偲傛 偼傞偐側摴傪丄偼傞偐側柌傪丂扵偟媮傔偰丄崱擔傕椃備偔丅 扵偟媮傔偰丄崱擔偧椃棫偮 偦偺嶌嬋壠彲巌棿偝傫傕乽僞僰僉僞僰僉偲屇偽傟偰偄傑偡偑乿偲垾嶢丅亀帪偺敔廙戞擇亁偺姰惉娫嬤偲偐丅偤傂丄婃挘偭偰傎偟偄丅 杒愳壝柧偝傫偐傜偼丄戝妛惗帪戙偺摦暔墍偺榖偑偁偭偨丅巹偑乽僑儕儔偼傒傫側惛恄昦偩乿偲尵偭偨偲偐丅杮恖傕朰傟偰偄偨愄偺榖偑弌偰偔傞偺偼丄偙偆偄偆強埲奜偵偼側偄丅 恊懓偐傜 懡偔偺曽乆偺垾嶢傪梊掕偟偰偄偨偑丄幚偵帪娫偑偨傝偢丄偙偺擔嶲壛偟偰偄偨偩偄偨恊懓偵暲傫偱傕傜偭偰丄墮偺暯栰棽堦偝傫乮奜柋徣乯偲挿彈偺壟偓愭偺嬍堜戝敧榊偝傫乮暯榓晄摦嶻夛挿乯偵丄偛垾嶢傪偄偨偩偄偨丅 墮偼晝恊偑帺塹戉偩偭偨偺偱丄摉帪廧傫偱偄偨嶰戲偵巹偑朘傟偨偙偲傪岅傝丄乽扤傕峫偊偮偐側偄傛偆側柺敀偄梀傃傪嶌偭偨乿偲偐丄乽偁傟偼悽奅偺僒儖偺杒尷抧丄壓杒敿搰偵偍偠偝傫偑峴偭偨帪偩偭偨偺偱偟傚偆乿側偳偲夰屆偟丄偦偺屻偺挊嶌丄偮偄偱偵斵偺巓偑崱夞偺杮偺昞巻奊傪昤偄偨偙偲傕徯夘偟偰偔傟偨丅偙偺壠宯偵偼丄偄傠偄傠摿暿嵥擻幰偑尰傟傞丅 嬍堜偝傫偐傜偼乽崱屻偲傕搰懽嶰偲傾僀傾僀丒僼傽儞僪傪傛傠偟偔乿偲偁傝偑偨偄偍尵梩傪偄偨偩偄偨丅嫲弅偺帄傝偲偼偙偺偙偲偱偟偨丅 搰懽嶰偐傜丂偙偺傛偆側奆偝傫偺尵梩偵椼傑偝傟偰丄杮棃偼姶幱偺尵梩傕懡乆尵偆傋偒偲偙傠丄嵟屻偺垾嶢偱傑偨偲傫偱傕側偄偙偲傪尵偄弌偟偨丅 乽偍傜偼丄戧戲攏嬚偵側傝偨偄乿偲丅 側傫傜偐偺暊埬傪帩偭偰偄傞偼偢傕側偔丄扨偵栚偑埆偔側偭偰偒偨偺偱丄攏嬚偑栍栚偵側偭偰傕亀敧將揱亁傪彂偒懕偗偨偙偲偵怗敪偝傟偨偩偗偺偙偲偱偟傚偆丅偟偐傕丄乽崱偟偽傜偔柪榝傪偐偗傞乿偲傕尵偭偰偄傑偟偨偹丅偙傟偼丄傑偨傛傎偳偺帠偐傕偟傟傑偣傫偑丄乽偄偄壛尭偵偟偨傎偆偑偄偄乿偲偺惡傕丅 亂嵎偟擖傟亃 嶳宍導暷郪巗偺媑郪彔條偐傜偡偽傜偟偄擔杮庰偑島択幮偵撏偗傜傟傑偟偨丅傒側傒側旤庰偵悓偭偨偼偢偱偡丅嶳宍弌恎偺僞僰僉偼堸傫偩偐偟傜丠 亂夛応偵偮偄偰亃 崱夞丄弌斉婰擮夛傪島択幮杮幮26奒嵟忋奒偺墐夛応偱奐偄偨偺偱偡偑丄偙傟偼傑偭偨偔梊憐傕偟側偐偭偨揥奐偱偟偨丅 偙偺杮偺姧峴偺偨傔偵丄側傫偳偐島択幮偵峴偒丄偦偺恾彂幒偺惁偝乮戝惓擭娫憂姧偺亀彮擭嬩妝晹亁傎偐偁傝乯偲尯娭惓柺偺壆撪怉暔墍偲偲傕偵3奒偺僇僼僃僥儔僗偺柧傞偝偵嬃偄偨偺偱偡丅偦傟偱丄偙偺僇僼僃側傜僷乕僥傿乕夛応偲偟偰傕巊偊傞偺偱偼側偄偐丄偲椦曈偝傫偵憡択偟偨偲偙傠丄乽偦偆偄偆夛応偼26奒偵偁傝傑偡乿偲偺偙偲偩偭偨丅偦傟偑偳傫側偲偙傠偐傕峫偊偢丄3奒偱偁傟傎偳峀乆偟偰偄傞偺偩偐傜丄26奒偼傕偭偲峀偄帇奅偩傠偆偲揔摉偵峫偊丄夛応傪梷偊偰傎偟偄偲偍婅偄偟偨偺偱偡偑丄偦傟偼椦曈偝傫偵偲偭偰偼幚偵偛柪榝側傾僀僨傾偩偭偨偲巚偄傑偡丅偝傑偞傑側幮撪庤懕偒偺塓傪偙偊偰丄傛偆傗偔夛応偑妋曐偝傟偨偲暦偄偰偄傑偡丅傎傫偲偆偵丄偡傒傑偣傫偱偟偨丅 偙偺夛応偵偼捈慜偵壓尒偵峴偭偰傃偭偔傝丅嵟戝400恖偑廂梕壜擻偱丄楯慻戝夛偲偐丄庴徿婰擮僷乕僥傿乕偲偐偵巊傢傟傞挱朷愨壚偺墐夛応偱偟偨丅偙傟傪尒偰丄乽偙偺夛応偑杽傑傞傎偳偺恖偑廤傑傞傢偗側偄偠傖側偄偐乿偲峫偊側偄偺偑丄儅僢僪側偲偙傠偱丄摢偵偁偭偨偺偼丄擔崰偍悽榖偵側偭偰偄傞傾僀傾僀丒僼傽儞僪偺奆偝傫偵丄島択幮杮幮偲偼偙傫側偲偙傠丄偲尒偣偨偄偲巚偆偽偐傝偱偟偨丅傑偨夛応偑寛傑傝丄偦偺挱朷偑暘偐偭偰偐傜丄乽偙傟偩偗栭宨偑偒傟偄側傜丄尒偵棃傞偩偗偱傕壙抣偑偁傞乿偲丄楢棈傪壛懍偝偣傞傛偆側偙偲偱偟偨丅 偙偺夛応偺傛偝偵偮偄偰偼丄摉擔弌惾偝傟偨傒側偝傫偑枮懌偝傟偨傛偆偱丄榓崄撧偝傫偼栭宨傪僗儅儂偱嶣偭偰丄偟偐傕曇廤偟偰娽壓傪憱傞崅懍摴楬偺岝偺塓傪僷僷偵尒偣偰偄傑偟偨丅  亂亀俋偮偺怷偲僔僼傽僇偨偪亁尨夋偺偙偲亃 媏扟偝傫偵儉儕傪尵偭偰帩偭偰偒偰偄偨偩偄偨偺偱偡偑丄偙偺惁偝両偤傂攷暔娰偐旤弍娰偱尨夋揥傪傗傝偨偄偲丄傑偨巚偭偨師戞偱偡丅 亂亀將幨恀揥亁偺偙偲亃 側偐偵偼尒側偐偭偨恖傕偄傞偐偲巚偄傑偡偑丄夛応偵偼杮偺拞偱巊偭偨幨恀傗儕儕乕夞屭偺幨恀丄悽奅偺將偨偪偺幨恀傪揥帵偟偰偄傑偟偨丅  亂亀僸僩丄將偵夛偆丂尵梩偲榑棟偺巒尨傊亁偵偮偄偰亃 偙偺杮偺崪奿偼丄亀僸僩乗堎抂偺僒儖偺堦壄擭亁乮拞岞怴彂乯偺堦晹偲偟偰彂偄偰偄偨傕偺偩偭偨偑丄偝偡偑偵堦壄擭傪堦嶜偺杮偱埖偆偺偼儉儕側偺偱丄偙偺將晹暘偼戝暆偵僇僢僩偟偰丄寢榑偩偗傪拞岞怴彂偵曻傝偙傫偱偍偄偨丅偦偺偨傔丄偙偺杮傪撉傫偩恖偼丄棟夝晄擻偵娮偭偨偐傕偟傟側偄丅 偦偺將栤戣傪偲傝偩偟偰傑偲傔傛偆偲偡傞偲丄恖乆偑撉傓偩偗偱媰偄偰偟傑偆傛偆側傕偺偲丄傑偭偡偖偵將乗恖娭學傪夝偒柧偐偦偆偲偡傞傕偺偲丄傆偨偮偺摴偑偁偭偨丅慜幰偼椡晄懌丅屻幰偼丄偲傝偐偐傝偩偗偼側傫偲偐偱偒偦偆丄偲偄偆偙偲偱丄偁偪偙偪偵乽彂偔偧丄彂偔偧乿偲彂偐側偄慜偐傜愰揱偟偰丄帺暘傪捛偄偮傔偰峴偭偨丅墦摗偝傫偑榖偝傟偨乽尋媶幒偺僨乕僞傪庢傝弌偟偰傑偲傔偨乿偲偄偆偺偼丄偙偺偁偨傝偺帠忣偱丄崱傑偱挷傋偰偙側偐偭偨將娭學偺榑暥傪戝検偵廤傔傜傟偨偺偼丄偡傋偰墦摗尋媶幒偺僔僗僥儉偺桪廏偝偺偍偐偘偩偭偨丅 傑偨丄僆僆僇儈偵偮偄偰偼丄僒儖偺栰奜挷嵏傪巒傔偨偙傠偐傜丄杮傗榑暥傪廤傔偰偄偨偙偲傕偁傝丄偦偺偄偔偮偐偼傑傞偱屆偄捑杤慏偺傛偆偵堄幆偺掙偵捑傫偱偄偨傕偺偱丄怴偟偄抦幆偵怗敪偝傟偰丄傐偐傝丄傐偐傝偲晜偒忋偑偭偰偒偨丅偦偺傂偲偮偑丄僼傽乕儗僀丒儌乕儚僢僩偺亀僆僆僇儈傛丄側偘偔側亁偩偭偨丅僨僀價僢僩丒儈乕僠偺戝挊亀僆僆僇儈亁傕摨偠崰丄擖庤偟偰偄偨偑丄報徾偺嫮偝偼柧傜偐偵儌乕儚僢僩偩偭偨丅偮傑傝丄巹偵偲偭偰偺將傊偺愙嬤偼1970擭戙屻敿丄嵿抍朄恖擔杮栰惗惗暔尋媶僙儞僞乕愝棫偺僪僞僶僞偺崰偵偼巒傑偭偰偄偨丅偟偐偟丄偦傟偼幚偵挿偄娫丄40擭埲忋傕婰壇偺汑掙偵捑傫偩傑傑偵側偭偰偄偨偺偩偭偨丅 廤拞偟偰偙偺杮偩偗偵偲傝偐偐偭偨偺偼丄2018擭9寧偐傜偩偭偨丅尨峞偺偡傋偰傪懪偪弌偟偰丄僐僺乕傪儅僟僈僗僇儖偵帩偭偰偄偒丄峴偒婣傝偺挿偄旘峴婡偺椃偺拞偱丄撉傒丄掶惓偟丄拲庍傪擖傟丄峔惉傪曄偊偨丅偄傛偄傛儅僟僈僗僇儖傪棧傟傞偲偄偆嬻峘儘價乕偺擇奒僇僼僃偱丄妸憱楬偲峀偄惵嬻傪尒側偑傜丄撍慠帇奅偑柧傞偔側傞偲偄偆宱尡傪偟偨丅摨帪偵丄乽偙傟偱傑偪偑偄側偄乿偲偄偆姶妎傕摼偨丅 偦偺姶妎側偟偵偼丄杮傪彂偔偙偲傪恑傔傜傟側偄偑丄偦偺姶妎傪暥復壔偡傞偙偲偼丄傑偨朿戝側帪娫偲庤娫傪梫偡傞偙偲偩偭偨丅擭枛擭巒偱偼偲偆偰偄廂傑傜偢丄堦寧偼庢嵽椃峴傪抐偭偰廤拞偟偨丅2寧偺孃楬楇壓27搙丄梻梻廡偺惵怷楇壓4搙偲偄偆姦嬻偺拞偱偺庢嵽傪廔偊偰丄傆偨偨傃杮偺姰惉偵廤拞偟丄3寧枛偮偄偵彂偒忋偘偨丅 偟偐偟丄偦傟傪撉傫偩曇廤幰偼丄寢榑晹暘偵乽傆偔傜傒乿傪梫朷偟偨丅嶍傞偺偼擄偟偄丅怢偽偡偺偼側傫偲偐側傞丅偟偐偟丄傆偔傜傑偣傞偺偼丄偙偲偵擄戣偱偁傞丅偩偑丄偦偺梫朷偺堄枴偼傛偔暘偐偭偰偄傞丅偦傟偼丄寢榑晹暘傊偺摓払偺巇曽偱偁傝丄嵟掅嶰曽岦偐傜寢榑偵岦偗偰徟揰傪峣偭偨偺偱丄偁傞偲偙傠偱偦傟埲忋偺愙嬤傪曻婞偟偨晹暘偑巆偝傟偰偄偨丅挊幰偲偟偰偼乽偙偙傑偱愙嬤楬傪峣偭偰偒偨偺偩偐傜丄寢榑偼摉慠暘偐傞偼偢偩乿偲偄偆婥帩偪偱偁傞丅懹枬偲偐汎傝偲偐丄偁傞偄偼旀傟偲偱傕尵偆傋偒傕偺偩偭偨丅擼偺椡偺偁傞尷傝傪傆傝偟傏偭偨偺偩偐傜丄偙傟埲忋偼儉儕丄偲偄偆姶妎偱傕偁偭偨丅 偟偐偟丄偦偙偵巆偝傟偨栤戣偑偁傞偙偲傕暘偐傞丅榑棟偑偳偺傛偆偵惗傑傟傞偺偐丄偦偺弖娫傪帺暘偑宱尡偟側偔偰偼側傜側偄丅 偦偟偰丄偁傞帪丄僘乕儉儗儞僘偺拞偺晽宨偺傛偆偵徟揰偑偁偭偰偒偨丅偦傟偼傏傫傗傝偟偨帇奅偵徟揰偑栠傝丄晽宨偑偼偭偒傝偲尒偊傞傛偆偵側傞姶妎丄偐偮偰愇堜懢榊塧応偺崅棞偠偄偝傫偑巹偺僯僐儞偺憃娽嬀傪擿偄偰尵偭偨乽尠旝嬀偺傛偆偵偼偭偒傝乿偲偄偆姶妎偩偭偨丅偙偺乽徟揰偑崌偭偨乿偲偄偆姶妎偼丄傑偡傑偡埆偔側傞栚偺戙懼偩偭偨偐傕偟傟側偄丅 傑偨丄偦傟偑乽傆偔傜傒乿偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅埨怱偟偰悽偵憲傝偩偡偙偲偑偱偒傞杮偑丄堦嶜偱偒偁偑偭偨弖娫偩偭偨丅 偙偺杮偼梊掕傛傝憗偔7寧弶傔偵姧峴偝傟偨偑丄偄傠偄傠側彂昡偑弌傞傛傝偼傞偐偵憗偔丄挬擔怴暦偺亀愜乆偺偙偲偽亁偱丄堦愡偑徯夘偝傟偨丅偦傟偑榟揷惔堦巵偱偁傝丄崌棟揑側尵梩偺婲尮偵怗傟偨揰偱丄偙偺杮偺妀怱傪偮偄偰偄偨丅嬃偔偺偼摉慠偱偁傞丅擔杮偺揘妛幰偵傕丄棟夝偱偒傞幰偑偄偨偺偐両偲丅 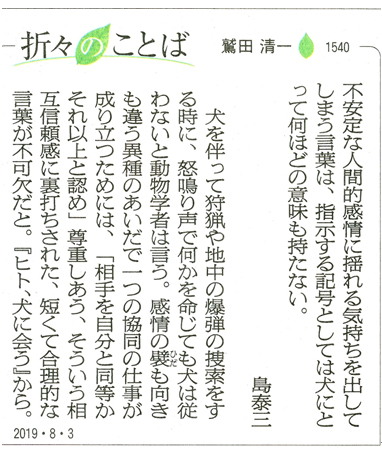 乮2019擭8寧3擔偺挬擔怴暦挬姧乽愜乆偺偙偲偽乿乯 乽愜乆偺偙偲偽乿偲尵偊偽丄擔杮偺偍傛偦偁傜備傞惗妶応柺傗暥復悽奅偱巊傢傟偨尵梩傪徯夘偡傞棑偱偁傝丄揤壓偺挬擔怴暦偺婄偲傕尵偆傋偒挬姧戞堦柺偺怓嶞傝僐儔儉偱偁傞丅偙偙偵堦暥偑堷梡偝傟傞偺偼丄暥復傪彂偄偰偒偨幰偲偟偰偼丄乽杮朷乿偲傕尵偆傋偒塰梍偱偁傞丅偱丄墱條偵偦傟傪帺枬偟偨丅 乽偡偛偄偩傠偆丅攎徳偺暥復傕堷梡偝傟偨僐儔儉側傫偩傛乿乽傆乣傫乿 乽壗丠偦偺婥偺側偄曉帠偼乿乽偩偭偰丄偦偺儗儀儖偠傖側偄偺丠乿 乽傂偊両扤偑乿丄乽偁側偨偑丄傛丅乿 丂乽偙傟偼僟儊偩乿偲娤擮偟偨丅嵢偵偼攎徳偲懽嶰偺嬫暿偑偮偄偰偄側偄丅偱丄懛偵尵偆丅 乽偡偛偄偩傠偆乿乽側傫偱丠乿 乽偩偐傜丄攎徳偑堷梡偝傟偨応強偱乿乽僕僕丄傑偨傊傫側僟僕儍儗傪尵偍偆偲偟偰側偄丠乿偙偺巕偺斀寕偵偼丄偄偮傕柺怘傜偆丅乽偩偭偰偝偁丄僶僔儑僂偲僶僔儑偱偟傚丅偦偆偄偆僟僕儍儗偱偟傚丠乿 丂偮偄偵慶晝偼搟傞丅 乽峊偊傛両堌傟懡偔傕偐偺徏旜攎徳側傞偧丅偄偔傜側傫偱傕戝妛庴尡偱擔杮巎偲偐丄擔杮岅偲偐傗偭偰傞傫偩偐傜丄偦傟偔傜偄妎偊偰偄傞偩傠偆丠乿 偄偔傜搟偭偰傕丄懛偼慶晝傪婥偺棙偄偨將偔傜偄偵偟偐巚偭偰偄側偄偐傜丄傑偭偨偔婥偵偟側偄丅 乽徏旜偐偳偆偐抦傜側偄偗偳丄僶僔儑僂偼暘偐傞丅曄側娍帤偩傛偹丅屆抮偩傛丅乿 乽偦傟偩両攎徳偲偄偊偽亀屆抮傗亁偺柤嬪偱擔杮恖側傜扤傕偑抦偭偰偄傞攐恖偱偁傝丄擔杮暥妛偺嵟崅曯偺傂偲傝偩丅偦偺暥偑堷梡偝傟偨攎徳偱丄偄傗丄僶僔儑偱丄傢偑暥偑堷梡偝傟偨偲偄偆偙偺柤梍傪偍慜偨偪偼棟夝偱偒側偄偺偐両乿乽儉儕儉儕乿 乽偊丠乿乽偩偭偰偝偁丄栱惗帪戙偲偐峕屗帪戙偺屆偄恖偩傛丄偦偺恖丅俙俲俛偲堘偭偰丄傎偲傫偳偺恖偼抦傜側偄恖偩傛丅偦傫側恖偲暲傫偱丄偆傟偟偄丠乿 懛偼擔杮巎偱庴尡偡傞偲偄偆偑丄攎徳偵偮偄偰偺帪戙擣幆偦偺傕偺偑偍偐偟偄偟丄屆偄偐偳偆偐傕傛偔暘偐傜側偔側偭偰偒偨偑丄攎徳偺尵梩偲側傜傇偙偲偼偆傟偟偔側偄丄傢偗偱偼側偄丅側傫偩偐旝柇偵側偭偰偟傑偭偨丅偦偙偱柕愭傪曄偊傞丅 乽巹偵偲偭偰偼丄偙偺挬擔怴暦堦柺偲偄偆偙偲偑廳梫側傫偩丅偪傚偆偳50擭慜丄僕僀僕偺柤慜偑偦偙偵嵹偭偨偐傜丄敿悽婭傇傝偲偄偆偙偲偵側傞丅乿乽側傫偱嵹偭偨偺丠乿 乽偊両丠乿乽偩偐傜丄怴暦堦柺偵柤慜偑嵹偭偨傫偱偟傚丄側傫偱丠乿 乽傑偁丄偪傚偭偲僪僕傗偭偰丄寈嶡偵偮偐傑偭偨偐傜乿乽僶僇偠傖傫両乿 擔杮巎偱偼丄偤傂愴屻巎傕嫵偊偰傎偟偄偟丄偦偺側偐偵埨揷島摪帠審傪娷傓慡崙妛墍摤憟偺帪戙傪偤傂壛偊偰傕傜偄偨偄傕偺偩丅妛惗偨偪偺斁棎偑乽僶僇偠傖傫両乿偺傂偲尵偱偍偟傑偄偵偟偰傎偟偔偼側偄丅偪傚偭偲愢柧傪偟偨丅 乽僕僀僕偨偪偑庒偐偭偨帪戙丄1960擭戙偵偼搶傾僕傾偱偼愴憟偑塓姫偄偰偄偨丅偦傟偼戞擇師悽奅戝愴偐傜懕偔愴憟偱丄儀僩僫儉偱偼傾儊儕僇偑楢擔丄旕恖摴揑側敋寕傗柉娫恖峌寕傪偟偰偄偨偐傜丄悽奅偺庒幰偨偪偼斀愴塣摦傪峀偘丄擔杮偱傕傎偲傫偳偺戝妛偱僗僩儔僀僉偑巒傑偭偨丅偦偺揤墹嶳偑搶戝埨揷島摪偺峌杊愴偩偭偨丅僕僀僕偼偦偙偱曔傑偭偨丅乿乽偮傑傝丄儀僩僫儉偺愴憟偵斀懳偟偨偺偱曔傑偭偨偭偰偙偲丠乿 乽偄傗丄戝妛偑嵾傕側偄妛惗傪偨偔偝傫戅妛張暘偵偟偨偺偱峈媍偟偰埨揷島摪傪愯嫆偟偰偄偨偐傜丄晄戅嫀偲偐偦偺傎偐傕傠傕傠偺嵾忬偑偁偭偨偗偳偹丅乿乽偱丄側傫偱僕僀僕偩偗偑怴暦偵柤慜偑嵹偭偨偺丠執偐偭偨偺丠乿 乽偄傗丄庡棫偭偨恖乆偺嵟屻偵乿乽偠傖偁丄巕暘傒偨偄側傕偺丠乿 乽偰偄偆偐丄傑偁亀嵟屻傑偱偑傫偽傝傑偟偨偹亁偭偰姶偠偐側偁乿乽偁偺偝丄巹偩偐傜偄偄偗偳丄傒傫側偵偼尵傢側偄傎偆偑偄偄偲巚偆傛丄50擭傇傝偵挬擔怴暦挬姧偺堦柺偩偲偐丅50擭慜偐傜婋側偄恖偩偭偰暘偐偭偰偄偨偭偰姶偠偱庴偗庢傞恖偑懡偄偲巚偆乿 僔儏儞丅 乽偄傗丄偪傚偭偲懸偰丅偙偙偵偼僕僀僕偺杮偺堦晹偑丄戝妛庴尡偱巊傢傟偨偲偄偆楢棈偑偁傞丅偳偆偩丄偙傟偵偼嬃偄偨偩傠偆丠乿乽偳偙偺戝妛丠乿 乽杒奀摴偺戝妛乿乽儈乕偼搶嫗偺戝妛傪庴尡偡傞傫偩傛丅娭學側偄偠傖傫乿 偙傟偼傎傫偲偆偱亀懛偺椡亁偺堦愡偑丄偁傞戝妛偺2018擭搙偺帋尡偵巊傢傟偨偺偩偭偨丅偟偐偟丄偦傟偱傕懛偺妋怣偼傃偔偲傕偟側偄丅側偵偟傠丄慶晝偑戝嵢彈巕戝偺彆嫵庼怑傪側偘偆偮偲偄偆棟夝晄擻偺偙偲傪偟偨偲抦偭偨帪丄乽僕僕偝偁丄戝嵢彈巕戝偭偰偡偛偄儗儀儖側傫偩傛丅偙傟偐傜偦偆偄偆偍桿偄偑偁偭偨傜丄抐傞傫偠傖側偄傛乿偲偒偮偔幎偭偨偺偑丄拞妛惗偺帪偱偁傞丅崱傗戝恖偺奒抜傪忋傝偮偮偁傞崅嶰偱偁傞丅偪偭偲傗偦偭偲偱偼丄僕僀僕傊偺懜宧怱偼惗傑傟側偄丅 偙偺夛榖偼8寧弶傔偺偙偲偱丄弌斉婰擮夛傊偺偍桿偄傪偼偠傔偰偄偨偙傠偩偭偨丅 乽2019擭9寧13擔嬥梛擔乮暓柵乯屵屻5帪傛傝7帪傑偱丗島択幮杮幮26奒夛媍幒偱乽弌斉婰擮夛乿乮巌夛丗惔悈夒巕條乯傪奐偒傑偡丅奆偝傑丄偍桿偄偁傢偣偱偍弌偐偗偔偩偝偄乿偲丅偁丄懛偼棃傞偐側丠 乽棃傞丠乿乽峴偐側偄丅崅嶰偩傛丄偦傫側娬側偄傛丅偁丄弇偺帪娫偩丅峴偐側偔偪傖丅傛偭偟傚丄偆両廳偭両乿 5嫵壢慡晹偺嫵壢彂嶲峫彂偵僲乕僩傪媗傔偨儕儏僢僋傪偐偮偄偱丄偱偐偗傑偟偨丅崱擔偼35亷丅尦婥側傕傫偩丅 偲傕偁傟丄8寧偍傢傝偵偼杮偺彂昡側偳偑弌傞傛偆偵側偭偨丅 嶨帍亀岞尋亁偱偼丄曇廤幰偑挌擩側徯夘傪偟偰偔傟偰丄乽搶撿傾僕傾偺撪棨傪傎偭偮偒曕偒偨偔側偭偨乿偲偄偆庤巻傪偔傟偨丅將偺婲尮抧傪曕偄偰傒偨偔側偭偨偲偄偆偺偼丄朖傔尵梩偩偲彑庤偵夝庍偟偰丄峀崘戙側偟偱愰揱偟偰偔傟偨丅傂偨偡傜偁傝偑偨偄丅  偦偙傊搶嫗怴暦傪撉傫偱偄偨嵢偑乽偄偄抦傜偣乿偲彂昡棑傪帵偡丅 搶嫗怴暦偺彂昡棑偺4暘偺1偵偁偨傞戝偒側彂昡偑丄偦傟傕僇儔乕昞巻擖傝偱宖嵹偝傟偰偄傞丅昡幰偼亀垽將墹暯娾暷媑揱亁乮彫妛娰乯側偳偱抦傜傟傞將偺杮傪彂偄偰偄傞曅栰備偐巵乮僲儞僼傿僋僔儑儞嶌壠乯偱偁傞丅偒傟偄側彂昡偵傑偲傔偁偘偰偔傟偨丅  斵彈偑偙偺杮傪撉傫偱丄乽摉弶偼將岲偒偺嬌榑乿偲巚偭偨偲偄偆偺偼丄幚姶偱偁傠偆丅懡偔偺恖偼丄巹偑墡岲偒偩偲偐丄僑儕儔岲偒乮偙傟偼杮摉乯偲偄偆懁柺偐傜昡壙偡傞偺偩偑丄岲偒寵偄偼戝偟偨栤戣偱偼側偄丅巹偑捛媮偟偨偄偺偼丄偦偺愭側偺偩丅 亀梼偺墹崙亁偺曇廤挿丄栧慜偝傫偼弌斉婰擮偵棃偰偔傟偰丄乽僷儞僟偺庢嵽側偺偵墡偱掆傑偭偰丄亀墡岲偒偼偳偆偟傛偆傕側偄側偁亁偲巚偭偨偗傟偳丄偁傞塮夋偱僑儕儔偺怷偵徚偊偰備偔庡恖岞傾儞僜僯乕丒僷乕僉儞僗傪尒偰丄搰偝傫偵廳側傝丄偦傟埲棃偼偦偆偄偆傕偺偐偲擺摼偟偰偄傑偡乿偲尵偭偰偔傟偨偑丄偦偺徚偊偰偄偭偨愭偑栤戣側偺偩丅 乽梊憐奜偺愢摼椡偵傂偒偙傑傟偨乿偲偄偆暥偵偼乽偵傗傝乿偲偟偨偹丅恖偼帺暘偺憐掕偟偨斖埻偱偺暥復嶌傝偵惛偩偟偰偄傞丅偦偆偱側偄偲丄偳偙偵峴偔偺偐暘偐傜側偄暥復偵側傞偐傜偩丅偟偐偟丄傂偲偮偺敪憐傪宍偵偡傞偨傔偵偼丄偛偔柺搢偔偝偄柍悢偺帠幚孮傪撍偒偸偗傞嶌嬈偑昁梫偵側傞丅偦偙偱傕偭偲傕廳梫側偺偼丄偦偺帠幚孮偑丄帺暘偺憐掕傪偙偊傞傎偳偵廤愊偝傟傞偙偲偱偁傞丅偦偺帪丄彂偄偰偄傞帺暘帺恎偑巚偭偰傕傒側偐偭偨抧暯偑奐偗傞偙偲偑偁傞丅偦傟偑丄偙偺傛偆側杮傪彂偔偲偒偺戠岉枴偱偁傞丅 偦偺乽曮憼帺偢偐傜奐偗偰乿偲偄偆弖娫偼丄偝傑偞傑側宍傪偲傞丅亀恊巜偼側偤懢偄偺偐亁偱偼丄偦偺弖娫偼挿偄儅僟僈僗僇儖偺幵偺椃偺搑拞偱偺妎惲偩偭偨丅乽媡偩両乿偲偄偆姶妎偱偁傞丅恖偼傾僀傾僀偺巜傪婏柇偩偲巚偆偑丄傾僀傾僀偐傜傒傟偽丄恖偺庤巜偺傎偆偑婏柇偩丅偦偺帇揰偐傜恖傪尒傟偽傛偄丄偲偄偆妎惲偩偭偨丅 亀偼偩偐偺婲尮亁偱偼丄乽幚偵孅嬋偺偁傞戝壨偵灗偝偟偰偒偨乿偲偁偲偑偒偱彂偄偨偲偍傝丄帠幚偺奜榞傪屌傔傛偆偲偟偰嶌嬈傪懕偗偰偄傞偲丄崱傑偱棳傟偰偒偨偲偼斀懳曽岦傊棳偝傟丄偝傜偵堦夞揮丄擇夞揮偲榑棟偺塓偵姫偒偙傑傟偨丅嵟屻偵僟乕僂傿儞庡媊傊偺姰慡側實暿偵帄傞榑棟偺戝壨偼丄幚偵巚偭偰傕傒側偄偙偲偽偐傝偩偭偨丅偦偺寖棳傪側傫偲偐忔傝偒偭偨偲帺暘偱巚偊傞偺偼丄偼偩偐偺旂晢偲偄偆恖娫偺摿挜偺堎忢偝傪乽堎忢乿偲偟偰姶偠傞惓忢側姶妎偩偭偨偲峫偊偰偄傞丅 偙傟傜偺悽忋偵傕偁傞掱搙昡壙偝傟偨杮偵斾傋傞偲丄亀僒儖偺幮夛偲僸僩偺幮夛亁乮戝廋娰彂揦乯偲亀僸僩乕堎抂偺僒儖偺堦壄擭亁乮拞岞怴彂乯偼丄悽娫揑偵偼傎偲傫偳柍帇偝傟偨斶偟偄杮偱偁傞丅 慜幰偼巹偲偟偰捈棫擇懌曕峴丄棁丄偦偟偰僸僩偺摿庩側幮夛偲偄偆儂儌丒僒僺僄儞僗棟夝偺偨傔偺嶰晹嶌偲偟偰峔惉偟偰偄傞丅僸僩偺幮夛偵偼丄奒媺惂傪傕偭偨僔儘傾儕傗傾儕傗僴僠偺傛偆側幮夛偵帡捠偭偨偲偙傠偑偁傞偙偲偑丄偦偺敪憐偺尨揰偱偁傝丄僒儖偨偪偑巕嶦偟偼偟偰傕僸僩偺傛偆側傢偑巕嶦偟偼偟側偄偙偲偺堄枴傪栤偭偨傕偺偩偭偨偑丄悽偺拞偼暯慠偲柍帇傪偟偨丅 屻幰偼丄椶恖墡偲偟偰偺恖椶偺偦傟偧傟偺楌巎揑抜奒偱偺偦傟偧傟偺庬偺僯僢僠偺夝柧偵傛偭偰偦偺惗懚曽朄偺摿堎惈傪柧傜偐偵偟偰偒偨丄偮傕傝偩偭偨丅偩偑丄楈挿椶偺婲尮偐傜擔杮恖偺尰戙偵傑偱偄偨傞偦偺帪娫偺偁傑傝偺挿偝偲弌尰偡傞椶恖墡偺庬悢偺懡偝偵丄扤傕偑鐒堈偟偨傜偟偔丄傑偲傕側彂昡偼尒傜傟側偐偭偨丅 崱夞偺亀僸僩丄將偵夛偆亁偼丄偦偆偄偆堄枴偱偼丄徟揰偑峣傜傟偰偄偨偟丄傛偒昡幰偵宐傑傟偨丅偒傢傔偮偗偼丄抮郪壞庽巵偩偭偨丅斵偺彂昡傪嫵偊偰偔傟偨偺偼丄壓娭偵偡傓彫揷堩巕偝傫乮惣崅屻攜丄尦惣崅嫵巘乯偩偭偨丅抦傝偁偄偺峑挿偐傜楢棈偑偁偭偨丄偲丅偁傢偰偰恾彂娰偵峴偒丄暵娰偓傝偓傝偱僐僺乕傪庢傞丅 斵偼亀恊巜偼側偤懢偄偺偐亁乮拞岞怴彂乯傪乽柤挊乿偲昡偟偨恖偱偁傞丅彫崟堦嶰偝傫偼乽抮郪偝傫偑嫽暠偟偰偄傑偡傛乿偲斵偺彂昡偑亀廡姧暥弔亁偵嵹偭偰偄傞偲楢棈偟偰偔傟偨傎偳偩偭偨丅崱夞傕丄抮郪壞庽巵偺帇揰偼傗偝偟偄丅  乽抦揑側夣姶乿偲尵偆丅杮傪撉傓偺偼丄幚偵偦偙偵偁傞丅帺暘偺拞偵惗傑傟傞暿悽奅偙偦丄杮傪撉傓戠岉枴偱偼側偄偐丅偦傟傪姶偠偰傕傜偊偨偲偟偨傜丄彂偒庤偲偟偰偼枮懌偱偁傞丅乽徻嵶側曬崘乿偲偁傞丅朻摢偺僀僲僔僔庪傝偼丄僼傿乕儖僪儚乕僋偺傛偆側傕偺偩偐傜丄僼傿乕儖僪僲乕僩偑偁傞丅徻嵶側偺偼丄傢偑婰榐偺忢偱偁傞丅 乽愖妛乿偲屇偽傟偨丅摴尦側傜乽愨妛柍堊乿偲尵偆偲偙傠偱偁傠偆偐丅偙偺偲偙傠丄恖偑埆偔側偭偰偄傞偺偱丄1970擭戙偵撉傫偩杮傑偱摦堳偟偰丄抦幆偺暆傪傂偗傜偐偟偰偄傞偲偙傠偑偁傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄抮郪壞庽巵傎偳偺恖偼閤偝傟側偄偩傠偆偐傜丄傑偁丄娒傫偠偰丄岲昡偲巚偆偙偲偵偟傛偆丅柺敀偄偺偼丄儅僟僈僗僇儖偱偺曐岇妶摦傑偱徯夘偟偰偔傟偨偙偲偱丄偙偺彂昡棑偺拞墰偵僨儞偲偍偐傟偨暥復偱丄杮埲奜偺挊幰偺妶摦傑偱徯夘偟偰偄傞偺偼丄偝偡偑偵彫愢壠偺帺桼偝偱偁傞丅 暪偣偰偁傝偑偨偐偭偨丅 杮偼彂偒庤偩偗偱偼姰寢偟側偄丅撉傒庤偑偄偰丄憡屳偵摼傞偲偙傠偑偁偭偰丄弶傔偰惉傝棫偮丅偦偺堄枴偱丄撉傒庤傪摼偨崱夞偺杮偼丄彂偒庤偵偲偭偰傕傎傫偲偆偵岾偣側杮偩偭偨丅 Copyright(C)2002-2025 Nihon Ayeaye Fund. All rights reserved. |